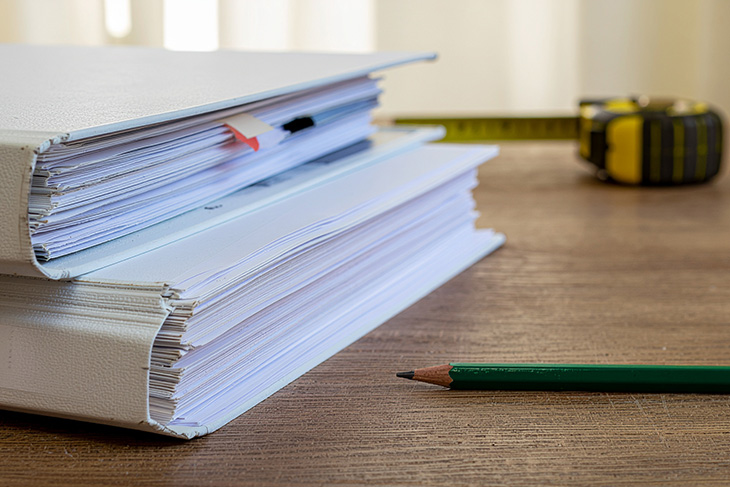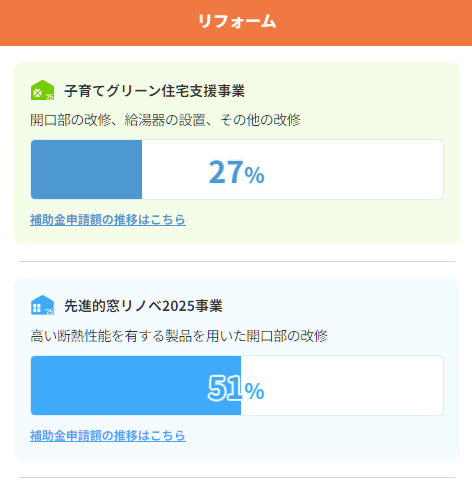神様を敬う ─ 御幣(ごへい)に託す、私たちとお施主さまの心
こんばんは
茨木市にある自然素材の注文住宅を建てる工務店、エッグ住まいる工房の勝田です。
上棟の日、骨組みが空に向かって立ち上がった棟木のそばで、厳かに取り付けられる小さな”しるし”があります。
それが今回採り上げる御幣と呼ばれているものです。
上棟式に欠かせない御幣なのですが、今回も前回に続き、日本文化にちなんだ話題でお送りします。

そもそも御幣って何
御幣は、清めや祓いを表す幣束(へいそく)に紙垂や榊をあしらったものです。
地域によって姿かたちに違いはありますが、意味はおおむね同じで、「ここから新しい営みが始まる」という境い目の印です。
上棟の折には、棟木や小屋束に向けて取り付け、屋根裏にそのまま納めておくのが一般的。見えないところで長く家族を見守る“守札”のような役割を担います。
似たものに棟札(むなふだ)があります。こちらは家の“履歴書”で、上棟の年月日や施主名、設計・施工の名を墨で記します。御幣と一緒に掲げる地域もあれば、別々に納める地域もあります。
向きや取り付け方にも土地ごとの作法がありますが、迷うときは棟梁や神職の判断に委ねるのがいちばん安心。形式に縛られすぎず、敬う心を形にすることが本筋です。
なぜ上棟式で使うの
上棟式で御幣を使う理由には3つのものがあるそうです。
① 場を整える(清めて、無事をお願いする)
上棟の日は、家が”建物”へと切り替わる節目にあたります。
御幣は「この土地で、安全に工事を進めます。どうか見守ってください」とお伝えする小さなしるしです。
上棟式はこれまでの感謝と、この先の安全祈願が目的とされていますので、気負うことなく、「はじめまして」と土地にあいさつするイメージで問題ありません。
② 人を整える(関わるみんなの気持ちをそろえる)
御幣の前に集まることで、お施主さま・設計士・大工さんが同じ方向を向くことができます。
まずは”安全配慮して住まいをつくる”ということを共通の思いとして、この節目の日にそれぞれの言葉を口にします。
そういう意味では上棟式は儀式でもあり、チームの空気を整える時間として考える日でもあります。
③ 時間を刻む(「今日」を未来に残す)
御幣といっしょに納めることの多い棟札(むなふだ)には、上棟の日付や名前などを書いたりします。
自治体の文化財解説でも、棟札は家づくりの記録として天井裏などに残してきた、と紹介されているように、ふだんは見えませんが、“この家はこの日に始まった”という記録を担います。
ちなみに上棟式の作法についてですが、正解はありません。
肩ひじをはる必要はありませんので、「この土地を敬い、工事の無事を願い、ここで始まる暮らしを大切にします」と静かに神様に伝えてくださいね。
〇注文住宅で新築を少しでもご検討されている方ご必見イベントのご紹介
・住まいづくりの大事なところを確認できる。構造・断熱見学会
(2025年11月30日10:00~16:30、大阪市都島区にて)